頸椎捻挫や腰椎捻挫などで、後遺障害等級の認定を得るのは難しいといわれています。これは本当でしょうか?
なぜ、頸椎捻挫などは後遺障害として認められにくいのか?
交通事故で頚椎捻挫・むちうち・腰椎捻挫と診断されるほとんどが自覚症状のみで、医師が診察をしても他覚所見を得る事が出来ません。つまり、症状の原因が客観的にはっきりとしません。
レントゲンやMRIに異常があったとしても加齢による症状とされる場合が殆どです。しかし、頚椎捻挫などでも後遺障害と判断される事があります。
よく言われる「医学的に立証できない症状は後遺障害として等級が認められない」「客観的で他覚的所見がないから後遺障害は認定されない」というのは「等級が認められない」「認定されない」と言い切るところが間違っています。確かに、「ムチウチでは後遺障害は難しい」といった多くの意見があるのは事実でそれは正しいです。しかし、このような自覚症状のみで他覚的所見のない頚椎捻挫・むちうち・腰椎捻挫のために、第14等級9号という後遺障害の等級が存在するのです。
もちろん、むち打ちなどに客観的な他覚所見である画像所見や神経学的所見が得られれば12級10号に該当する事になります。
頸椎捻挫、腰椎捻挫の等級
ところで、一般的に頚椎捻挫・むちうち・腰椎捻挫が後遺障害と認められるときは次の等級に該当します。
 むちうち等の後遺障害認定基準
むちうち等の後遺障害認定基準
14級9号 (局部に神経症状を残すもの)
労働には通常差し支えないが、医学的に説明可能な神経系統の障害を残す所見があるもの。
12級10号 (局部に頑固な神経症状を残すもの)
労働には差し支えないが、医学的に証明できる神経症状をいう。

しかし、頚椎捻挫・むちうち・腰椎捻挫由来の痛みや痺れ、頭痛などの症状が強く残っているのにも関わらず、後遺障害の等級が取れないという相談を多く頂きます。
等級が非該当になる理由は、「将来回復すると思われるから」もしくは「症状が強くない」といった2つが多く、このように判断されてしまう原因の8割は症状固定、つまり後遺障害診断書を作成するまでに、書類上で確認できる何らかの問題があります。
頚椎捻挫・むちうち・腰椎捻挫で後遺障害が認められるとき
頚椎捻挫や腰椎捻挫で後遺障害が認定された時に自賠責から送られてくる認定理由(別紙)は、
「骨折等の明らかな外傷性変化は認めがたく、その他診断書等からも、症状の裏付けとなる客観的な医学的所見に乏しい事から、他覚的に神経系統の障害が証明されたものとは捉えられません。しかしながら、治療状況、症状推移なども勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられる事から「局部に神経症状を残すもの」として別表第二表第14級9号に該当するものと判断します。」
というのが定型文章です。この認定理由(別紙)では治療状況と症状推移を理由として後遺障害の等級が認定されているところに注目してください。
つまり、これは被害者が>交通事故で受傷をして、初診を経て治療を行い、数か月治療・リハビリを行い、その間に適時適切な検査を経て後遺害診断書を作成する<というこの全ての流れが等級の認定理由であると説明しているのです。
よって、頚椎捻挫・むちうち・腰椎捻挫で正しい後遺障害としての評価を受けるには交通事故の発生日から出来るだけ早い時期に適時適切な対策をはじめる事で等級認定が望めます。
ここで注意をしたいのが、後遺障害診断書の作成の時(症状固定時)に、何も対策をしなかったからと言って「既に時遅し」と諦める必要はないという事です。後遺障害作成時に対応を行えば間に合う場合もかなり多く、仮に後遺障害診断書の作成を行ってしまったとしても、後遺障害の結果が出ていなければ、まだまだ対策は可能です。
それでも、すでに等級非該当の結果が出てしまっている場合は、後遺障害に対する異議申し立てという方法があります。ただし、症状固定までに等級認定に不利な事実が確認できてしまっていると、後遺障害と認められることはありません。

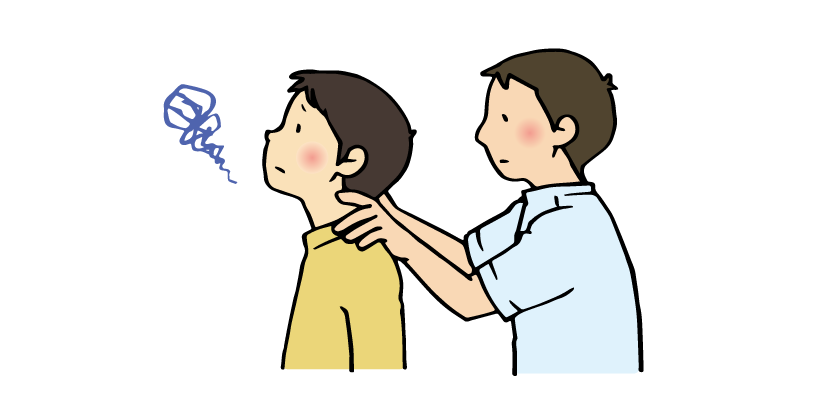
このページでコメント、FAQ(無料) 匿名、無料でご利用いただけます。
去年の9月に
帰りがけに十字路から車が左折しようと停車してて
自分は歩きでしたので、注意しながら歩道を歩いてたのですが
相手の車が右から来る車しか見ていなく
引かれました。
結果は 腰椎打撲 脛椎打撲 右半身打撲 右肘裂傷
と診断され
半年間通院していましたが、長時間座ると腰が痛く
車の運転や、仕事柄重い荷物を運んでたのですが。
50キロ位の物しか持てなくなりました。
事故前の私なら100キロ位は軽く持てていたのに仕事に支障を来してしまってる状態です。
首は回りますが、偏頭痛が良く起きる様になり
首の後ろの骨らへんがバットで殴られる様な痛みも出ます。
MRIは撮りましたが神経系の病院には行きませんでした。
まだ、昔のように本調子みたいに体が動かせるのでしょうか?
休業損害も本来働いてたらかなり貰えてた筈の給料も10万位、月で変わってたので本来の休業保証が意味が無く思えます。
質問します。昨年9月に車を車庫に入れようとして後方をよく確認しなくて電柱に衝突してしまい慌ててプレーキを踏んで翌日になって後頭部の痛みで整形外科に通い頭部挫傷、頚部挫傷、左下腿挫傷と診断され、湿布、リハビリに半年通いました。半年で約60日通いました。後遺症診断書も書いて頂きましたが認定されますでしょうか?ちなみに現在も後頭部の痛み、しびれが残り病院に通っています。
しびれが事故直後から発生していれば等級に該当する可能性はあるとおもいます。しかし、経験則からいえば非該当の可能性のほうが高いです。
質問させて頂きます。半年前に自家用車でバックで車庫に入れようとしたら電柱にぶつけてしまい整形外科にて脛椎挫傷、頭部挫傷と診断され当初は痛み止めを服用し改善されない為リハビリに変えて診療していましたが痛みとしびれが改善されない為後遺症診断書を書いてもらいました。果たして後遺症として認定されますでしょうか?
この場合重要なのはどのくらい治療を施した化であると思われます。あとは、事故時の衝撃の度合いも参考になるものです。
お忙し中、先日、私からの相談事に返信頂きありがとうございます。数日後弁護士より何らかの回答が来ると思いますので、今後先生に、すべて一任したいと思いますので、宜しくお願い致します。できれば、連絡先を教えて頂ければ有難く存じます。今後とも宜しくお願い致します。
後遺障害のサポートについてのご依頼はこちらから承ります。
ご検討ください。
2013年7月に信号待ちしているとき、後部より追突され近くの病院に2015年3月31日まで(485日実質日数)通院致しました。保険会社(東京海上日動)の担当者より後遺障害の申請をしますので、病院の先生に相談して書類を書いて貰ってくださいとの依頼がありましたので、先生に渡し作成致しましたところ、症状固定と言う書類を頂きましましたので保険会社に送付いたしましたところ、いきなり、今後は、自費で治療をして下さいと言われました。そのときは、永く通院していましたので仕方がないと思い、現在も自費で治療しています。休業損害補償については2015年5月分までは、頂いてると思います。(明細書が無い為不明)です。本題に入りますが、①休業損害補償については担当者にはしばらく仕事復帰はできませんのでと通達していましたので、休業損害補償の書類(2015年6月より2015年11月迄の書類と2015年8月分の賞与減額証明書を送付していました。本日2015年12月4日にあまり連絡がないので、こちらから担当者に電話したところ、休損は出せませんと言う返事でした(当時の話では治療費は打ち切りと言うことは聞いていました)。今日になって、担当者の方は休業損害補償についても打ち切りですと言う回答でした。この件に対しても納得出来ません。②慰謝料の問題ですが、本来私は、椎間板ヘルニアの手術5回、頸椎ヘルニア手術3回のしていますので、今回の事故により左足に痛みが起き佐田病院で手術を致しました。(保険会社確認済)この件に関しても因果関係の割合を持ち出して来ています。この件に関しては弁護士に一任しますのでお待ちくださいとの事です。連絡があり次第貴社先生にお力をお借りできればと思い、メールを送信した、次第です。宜しくお願い致します。
、
症状固定後の通院費は自費となります。そして、休業補償は受けられず、代わりに後遺障害の逸失利益という形で賠償されます。
たしかに、症状固定後の賠償金の支払いについて、保険会社の説明が足りなかったように思えますが、現状では「因果関係の割合を持ち出して」とあるとおり、いわゆる素因減額が大きな問題と考えられます。この話になれば、過去の治療費なども事故との因果関係を持ち出されかねません。おそらく今後は、症状固定の有り方についてよりも、素因減額について話し合いを持つことになると思われます。
去年の9月に
帰りがけに十字路から車が左折しようと停車してて
自分は歩きでしたので、注意しながら歩道を歩いてたのですが
相手の車が右から来る車しか見ていなく
引かれました。
結果は 腰椎打撲 脛椎打撲 右半身打撲 右肘裂傷
と診断され
半年間通院していましたが、長時間座ると腰が痛く
車の運転や、仕事柄重い荷物を運んでたのですが。
50キロ位の物しか持てなくなりました。
事故前の私なら100キロ位は軽く持てていたのに仕事に支障を来してしまってる状態です。
首は回りますが、偏頭痛が良く起きる様になり
首の後ろの骨らへんがバットで殴られる様な痛みも出ます。
MRIは撮りましたが神経系の病院には行きませんでした。
まだ、昔のように本調子みたいに体が動かせるのでしょうか?
休業損害も本来働いてたらかなり貰えてた筈の給料も10万位、月で変わってたので本来の休業保証が意味が無く思えます。
質問します。昨年9月に車を車庫に入れようとして後方をよく確認しなくて電柱に衝突してしまい慌ててプレーキを踏んで翌日になって後頭部の痛みで整形外科に通い頭部挫傷、頚部挫傷、左下腿挫傷と診断され、湿布、リハビリに半年通いました。半年で約60日通いました。後遺症診断書も書いて頂きましたが認定されますでしょうか?ちなみに現在も後頭部の痛み、しびれが残り病院に通っています。
しびれが事故直後から発生していれば等級に該当する可能性はあるとおもいます。しかし、経験則からいえば非該当の可能性のほうが高いです。
質問させて頂きます。半年前に自家用車でバックで車庫に入れようとしたら電柱にぶつけてしまい整形外科にて脛椎挫傷、頭部挫傷と診断され当初は痛み止めを服用し改善されない為リハビリに変えて診療していましたが痛みとしびれが改善されない為後遺症診断書を書いてもらいました。果たして後遺症として認定されますでしょうか?
この場合重要なのはどのくらい治療を施した化であると思われます。あとは、事故時の衝撃の度合いも参考になるものです。
お忙し中、先日、私からの相談事に返信頂きありがとうございます。数日後弁護士より何らかの回答が来ると思いますので、今後先生に、すべて一任したいと思いますので、宜しくお願い致します。できれば、連絡先を教えて頂ければ有難く存じます。今後とも宜しくお願い致します。
後遺障害のサポートについてのご依頼はこちらから承ります。
ご検討ください。
2013年7月に信号待ちしているとき、後部より追突され近くの病院に2015年3月31日まで(485日実質日数)通院致しました。保険会社(東京海上日動)の担当者より後遺障害の申請をしますので、病院の先生に相談して書類を書いて貰ってくださいとの依頼がありましたので、先生に渡し作成致しましたところ、症状固定と言う書類を頂きましましたので保険会社に送付いたしましたところ、いきなり、今後は、自費で治療をして下さいと言われました。そのときは、永く通院していましたので仕方がないと思い、現在も自費で治療しています。休業損害補償については2015年5月分までは、頂いてると思います。(明細書が無い為不明)です。本題に入りますが、①休業損害補償については担当者にはしばらく仕事復帰はできませんのでと通達していましたので、休業損害補償の書類(2015年6月より2015年11月迄の書類と2015年8月分の賞与減額証明書を送付していました。本日2015年12月4日にあまり連絡がないので、こちらから担当者に電話したところ、休損は出せませんと言う返事でした(当時の話では治療費は打ち切りと言うことは聞いていました)。今日になって、担当者の方は休業損害補償についても打ち切りですと言う回答でした。この件に対しても納得出来ません。②慰謝料の問題ですが、本来私は、椎間板ヘルニアの手術5回、頸椎ヘルニア手術3回のしていますので、今回の事故により左足に痛みが起き佐田病院で手術を致しました。(保険会社確認済)この件に関しても因果関係の割合を持ち出して来ています。この件に関しては弁護士に一任しますのでお待ちくださいとの事です。連絡があり次第貴社先生にお力をお借りできればと思い、メールを送信した、次第です。宜しくお願い致します。
、
症状固定後の通院費は自費となります。そして、休業補償は受けられず、代わりに後遺障害の逸失利益という形で賠償されます。
たしかに、症状固定後の賠償金の支払いについて、保険会社の説明が足りなかったように思えますが、現状では「因果関係の割合を持ち出して」とあるとおり、いわゆる素因減額が大きな問題と考えられます。この話になれば、過去の治療費なども事故との因果関係を持ち出されかねません。おそらく今後は、症状固定の有り方についてよりも、素因減額について話し合いを持つことになると思われます。